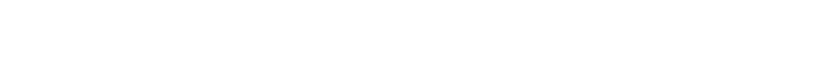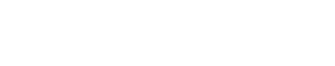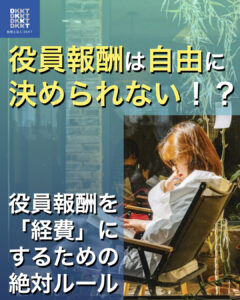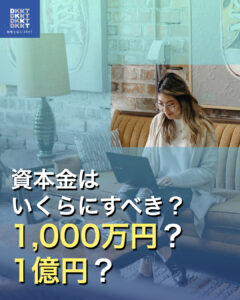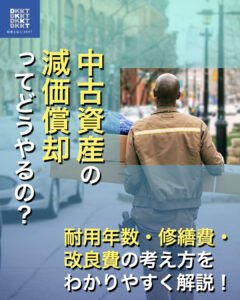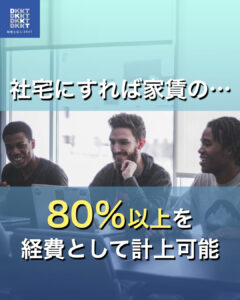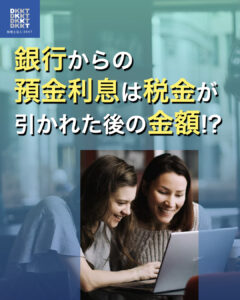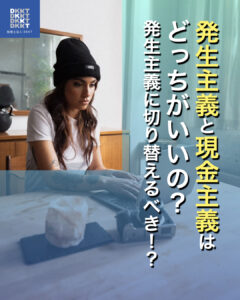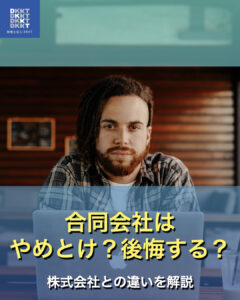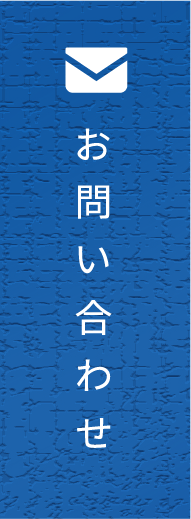創業前の費用も経費にできる!?開業費と創立費について解説
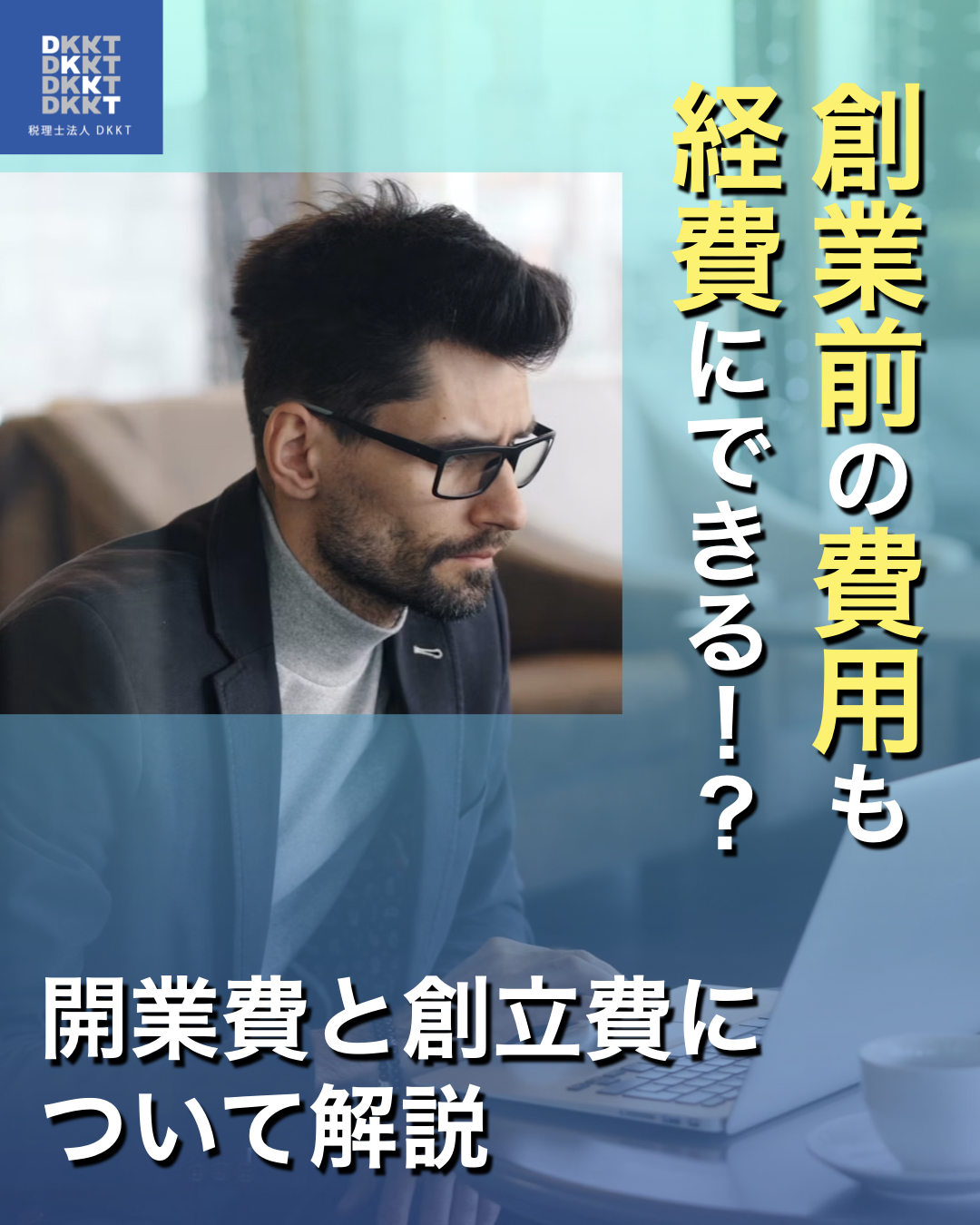
会社を立ち上げる際、事業を始める前から様々な費用がかかります。「まだ売上がないのに、こんな費用は経費になるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実は、会社設立や開業にかかった費用は、特定の条件を満たせば「経費」として認められます。
今回は、創業前の費用として代表的な「創立費」と「開業費」について、その違いや、賢く経費にするためのポイントを解説します。
1.創業前の費用は「繰延資産」として経費にできる
まず知っておきたいのは、創業前にかかった費用は、税務上「繰延資産」という特殊な資産として扱われる点です。これは、本来は費用ですが、その効果が将来にわたって継続すると考えられるため、すぐに全額を経費にするのではなく、少しずつ分割して経費として計上していく資産のことです。
この繰延資産として認められるのが、主に「創立費」と「開業費」なのです。
2.創立費とは?「会社設立にかかる費用」
創立費とは、その名の通り、「会社を設立するためにかかった費用」のことです。事業を開始する以前に発生する費用であり、会社の「産声」を上げるために必要な経費と言えます。
具体的には、以下のようなものが創立費に該当します。
- 発起人の報酬: 会社設立の準備に携わった人、つまり発起人(会社の発案者)への報酬です。
- 会社設立のための専門家報酬: 会社の設立手続きを司法書士や行政書士に依頼した場合に支払う手数料などです。
- 定款(会社のルールブック)の作成費用: 公証役場での認証手数料や収入印紙代などです。
- 登録免許税: 会社を登記する際に国に支払う税金です。
これらの費用は、会社が「法人格」を得るための費用であり、事業の内容とは直接関係なく発生する点が大きな特徴です。
3.開業費とは?「事業を始めるためにかかった費用」
一方、開業費とは、「会社設立後から事業を始めるまでの期間に、事業を円滑に運営するためにかかった費用」のことです。こちらは、会社という「器」ができた後に、その「器」で何をどうやって行うかを準備するための経費と言えます。
具体的には、以下のようなものが開業費に該当します。
- 広告宣伝費: 事業開始を顧客に知らせるためのチラシやウェブサイト制作費などです。
- 市場調査費: 顧客ニーズや競合他社の動向を把握するための調査費用です。
- オフィスの賃借料: 事業を開始する前のオフィスの賃借料や内装工事費、敷金・礼金なども含まれます。
- 従業員の給料: 準備期間中に従業員に支払う給料です。
開業費は、事業を始めるために必要な「準備期間」に発生する費用であり、その期間は会社の事業内容や規模によって様々です。
4.費用を計上するタイミングは?「任意償却」と「均等償却」
創立費と開業費は、どちらも「任意償却」が可能であり、会社が好きなタイミングで費用として計上できるという大きなメリットがあります。
この任意償却を有効活用することで、会社の利益状況に合わせて賢く節税対策を行うことができます。例えば、会社設立初年度は利益が赤字になる見込みなので、これらの費用を計上せずに翌年以降に繰り越すことが可能です。そして、利益が出始めた年にまとめて償却することで、その年の税負担を大きく減らすことができます。
また、もう一つの選択肢として、「均等償却」を選ぶこともできます。これは、5年間で均等に費用として計上していく方法です。100万円の開業費がかかった場合、事業開始等のタイミングからから5年間、毎年20万円ずつ経費として計上していくことになります。
どちらの方法を選ぶかは、会社の利益見込みや経営戦略によって判断することができます。
5.まとめ:起業家が知っておきたいポイント
| 項目 | 創立費 | 開業費 |
| 発生時期 | 会社設立前 | 会社設立後、事業開始まで |
| 費用の具体例 | 登録免許税、専門家報酬など | 広告宣伝費、備品購入費など |
| 税務上の扱い | 繰延資産 | |
| 費用計上 | 任意償却または均等償却(60か月) | |
創立費と開業費は、名前が似ていますが、発生する時期と費用の中身が大きく異なります。しかし、どちらも「任意償却」が可能であり、会社の経営状況に合わせて柔軟に費用計上できる点が共通のメリットです。
- 創立費は「会社の設立」のため
- 開業費は「事業の開始」のため
この明確な違いを理解しておくことで、経理処理をスムーズに進め、賢く節税対策にも役立てることができます。領収書や請求書は、どちらの費用に該当するかを明確にして保管しておくことが重要です。
起業家にとって、事業を成功させるためには、お金の流れを正しく把握することが不可欠です。創立費と開業費の違いをしっかりと押さえて、賢いスタートを切りましょう。