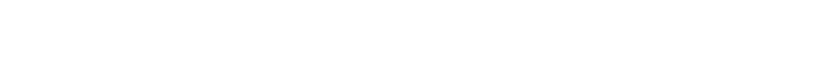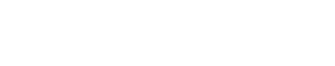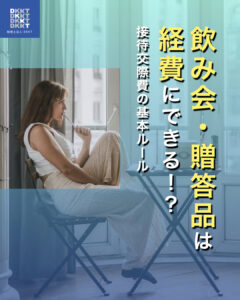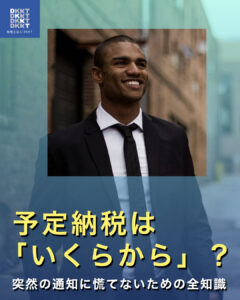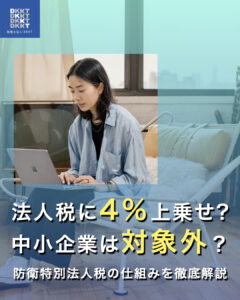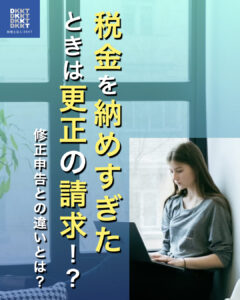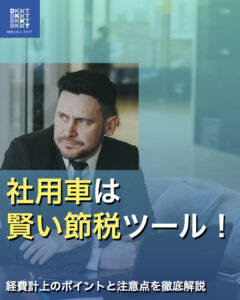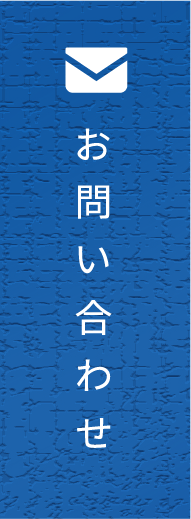銀行からの預金利息は税金が引かれた後の金額!?~受取利息の会計処理と税務の基本~
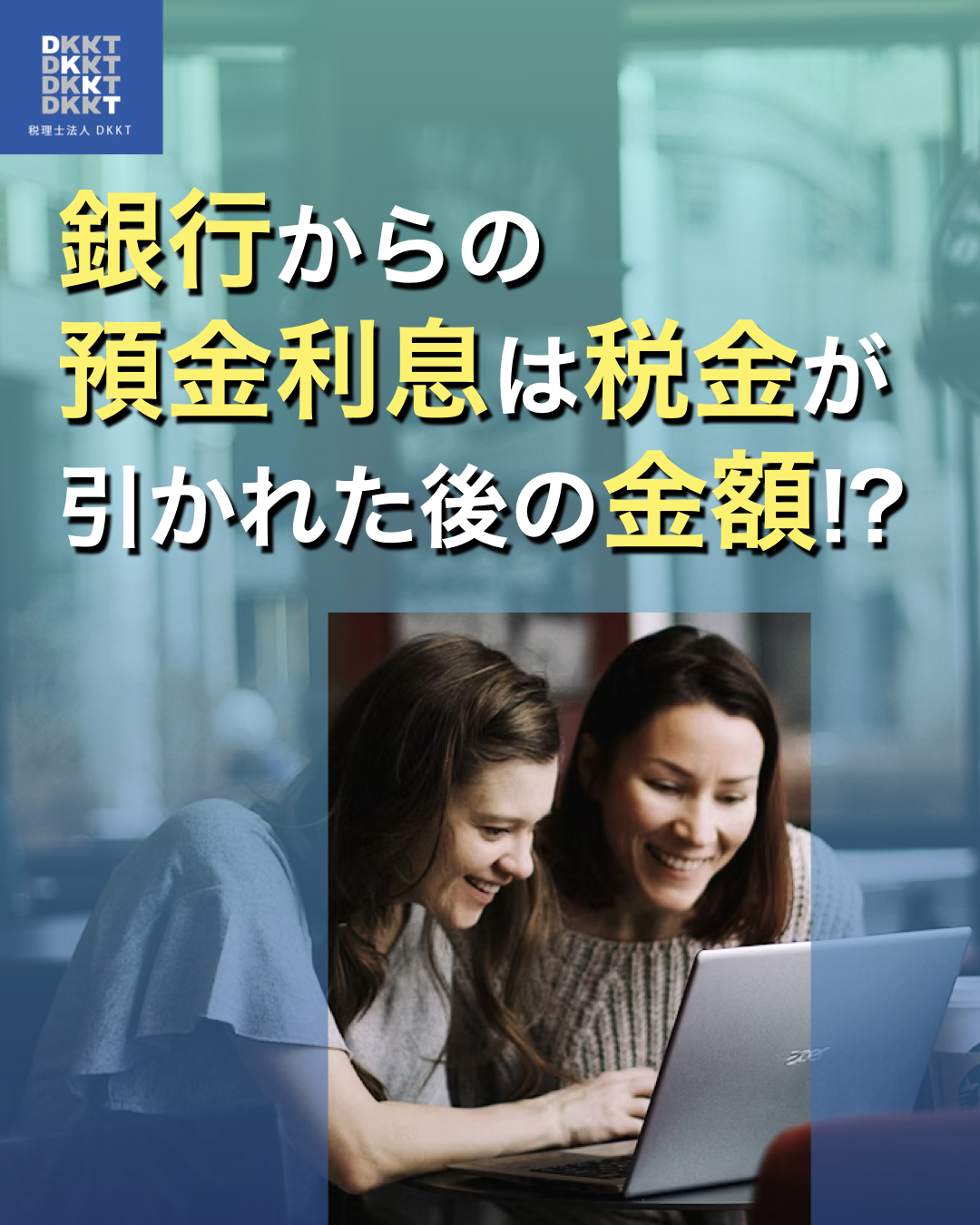
1.預金利息には税金がかかっていることを知っていますか?
普通預金や定期預金などに預金していると金額に応じて利息がつきます。普通預金の場合、多くの金融機関では年2回、2月と8月に利息が支払われ、預金口座に入金されます。
しかし、ここで注意が必要なのは、通帳に記載されている利息の金額は「税引き後」の金額であるということです。つまり、利息が支払われる際にはすでに税金が差し引かれていて、その残りの金額だけが実際に入金されています。
会計処理を行う際には、この差し引かれた税金を正確に把握し、「本来の利息の総額(税引前)」と「差し引かれた税金の額」を明らかにしたうえで処理する必要があります。
今回は、この「預金利息にかかる税金の正体」と「会計処理の実務」について、法人の場合と個人事業主との違いにも触れながら詳しく解説します。
2.利息から引かれる税金とは?個人事業主か法人かで違いはあるの?
◼︎ 法人の場合
会社が銀行から利息を受け取る際には、源泉所得税(15%)と復興特別所得税(0.315%)が自動的に差し引かれた後の金額が、銀行口座に入金されます。つまり、利息の総額のうち、15.315%分があらかじめ税金として控除されているのです。
◼︎ 個人事業主の場合
個人が銀行に預金して得た利息も、20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、銀行の預金通帳に利子の金額が表示された時点で、すでに所得税が引かれているため、確定申告をする必要はありません。
| 税率 | 税金の内訳 | |
| 法人 | 15.315% | 所得税15% 復興税0.315% |
| 個人 | 20.315% | 所得税15% 復興税0.315% 住民税5% |
3.源泉徴収された税金の計算方法と会計処理
法人が実際に利息を受け取った時の会計処理を行うための計算方法を見てみましょう。
法人が銀行から利息を受け取った際の会計処理には、「原則的な処理(税引前処理)」と「純額処理(税引後処理)」の2つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、会社の方針や事業規模に応じて判断することが重要です。
◼︎ 原則的な処理(税引前処理)
たとえば、預金口座に 8,469円 の利息が入金されていた場合、これは「税引後」の金額です。利息の総額(税引前)を逆算するには、以下の計算式を用います:
税引前の利息 = 入金額 ÷ (100% - 15.315%)
= 8,469円 ÷ 84.685% ≒ 10,000円
続いて、源泉徴収された税額はこうなります:
源泉税額 = 税引前利息 × 15.315%
= 10,000円 × 15.315% = 1,531円(端数切捨て)この計算結果を用いて受取利息の総額と差し引かれた税金の金額をそれぞれ仕訳に計上します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 普通預金 8,469円 | 受取利息 10,000円 |
| 法人税等 1,531円 |
※「法人税等」は損益計算書の項目で、法人税や住民税、事業税などを含みます。
この処理の最大のメリットは、法人税申告時に源泉所得税等を「所得税控除」として精算できることです。さらに赤字の場合には、差し引かれた税金の還付を受けることも可能です。
ただし、原則処理を行うためには、法人税申告書に以下の別表を記載する必要があります:
- 別表一(一):普通法人等の確定申告書
- 別表四:所得の金額の計算に関する明細書
- 別表六(一):所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
このように、税務上のメリットがある反面、申告や仕訳の手間が増えるのがデメリットです。
◼︎ 純額処理(税引後処理)
一方、利息の入金額(税引後の金額)だけを仕訳にするのが純額処理です。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 普通預金 8,469円 | 受取利息 8,469円 |
この方法はとてもシンプルで、源泉所得税の計算も不要で、仕訳も税務処理も手間がかからないのが大きな利点です。その反面、源泉徴収された税金については所得税控除ができず、還付も受けられません。
◆ よくある質問(FAQ)
Q1:通帳に記載された利息額がそのまま収入になるの?
A1:上記の通り、通帳に記載された金額は、すでに税金が差し引かれた「税引後の金額」です。帳簿上の収入としては、税引前の金額(源泉税額を含む)を計上する必要がありますが、通帳に記載された利息額をそのまま計上する純額処理も認められています。
Q2:通帳に税額が記載されていないけど、どうやって計算する?
A2:入金額から逆算する必要があります。たとえば、預金利息が8,469円入っていた場合は、8,469円 ÷ 0.84685 ≒ 10,000円が税引前の利息です。税額はこの差額の1,531円です。
Q3:受取利息が少額だけど、わざわざ仕訳しないとダメ?
A3: 金額の多寡に関係なく、法人会計ではすべて仕訳が必要です。個人事業主の場合、簡易簿記で申告している方は省略することもあります。
Q4:ネット銀行の利息にも同じように税金がかかる?
A4:はい。金融機関の種類にかかわらず、銀行からの利息であれば同じく源泉徴収されます。ネット銀行も例外ではありません。
◆ まとめ
銀行預金から得られる利息は、一見すると小さな金額に思えるかもしれませんが、実は税金が差し引かれた「税引後」の金額です。
法人・個人いずれの場合も、自動的に源泉徴収される仕組みになっており、通帳に記載される金額だけを見て会計処理してしまうと、税額控除のチャンスを逃すこともあります。
仕訳には「原則処理」と「純額処理」があり、それぞれに実務の簡便さと税務上のメリットという特徴があります。
- 少額なら「純額処理」で手軽に
- 赤字や大口利息が見込まれるなら「原則処理」で還付の可能性も
事業規模や会計方針に応じて、最も合理的な方法を選ぶことがポイントです。今回の内容を通じて、日々の会計処理をより正確に、そして戦略的に進められるヒントになれば幸いです。