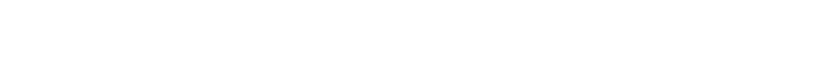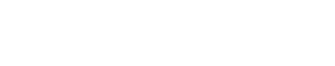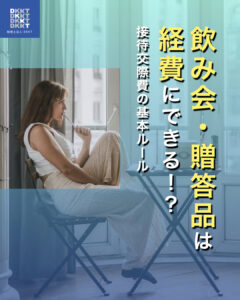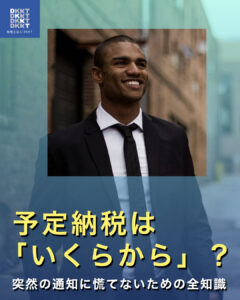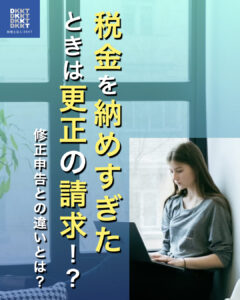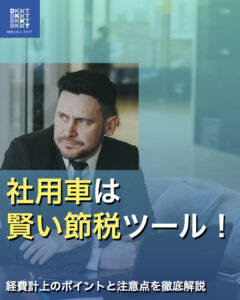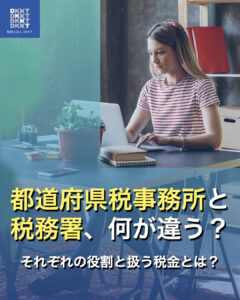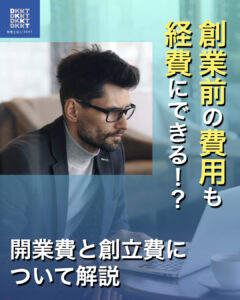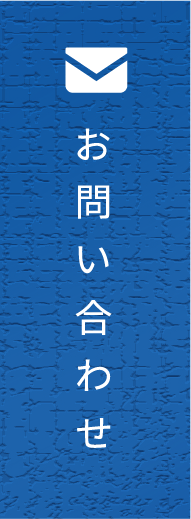法人税に4%上乗せ!? 中小企業は対象外?防衛特別法人税の仕組みを徹底解説
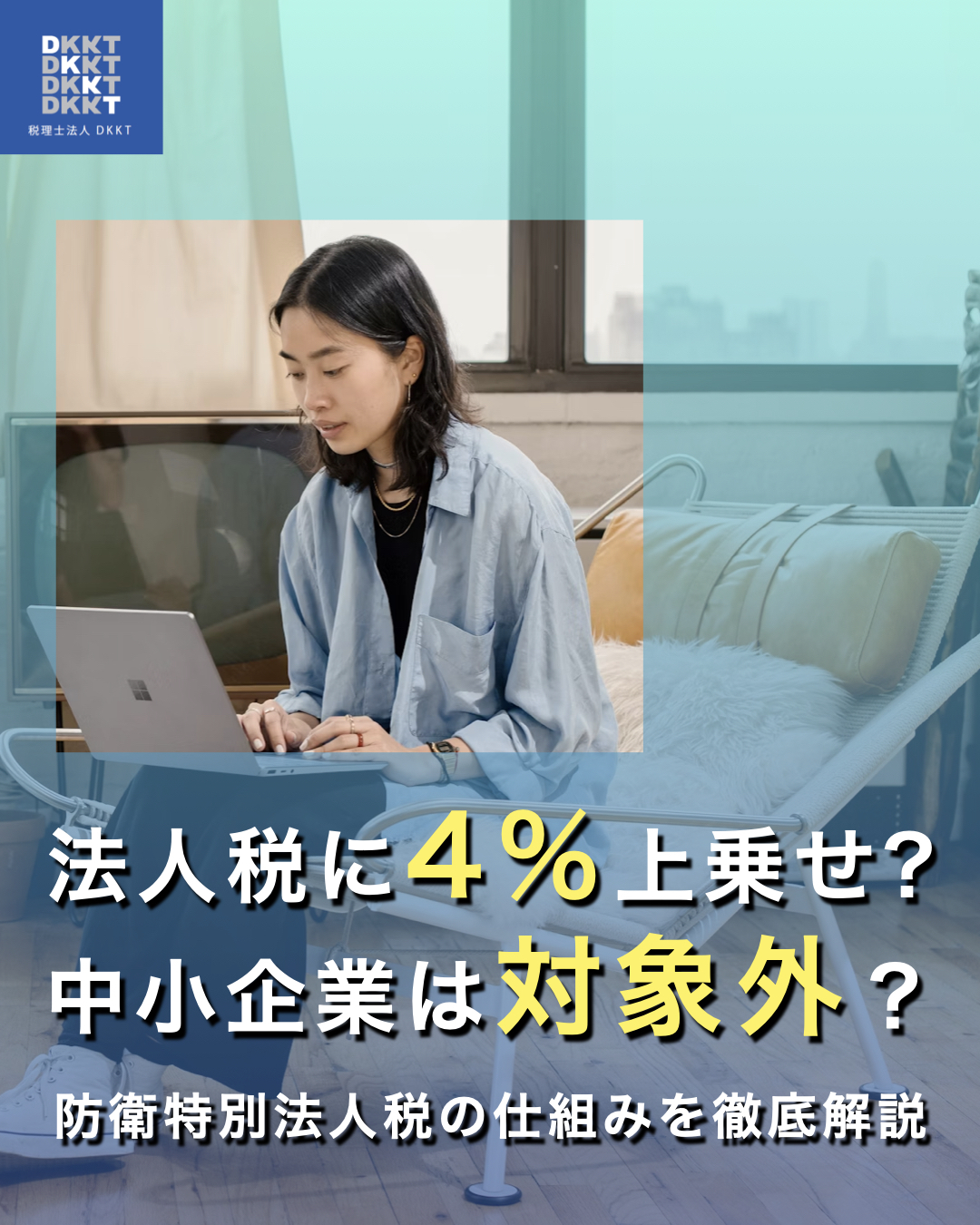
政府が打ち出した防衛力強化の財源を確保するため、「防衛特別法人税」の創設が決定しました。これは、既存の法人税に上乗せして課される新たな税金であり、企業の税負担が増加することになります。
「うちの会社も対象になるのか?」「いつから始まるのか?」「具体的にどれくらい負担が増えるのか?」—多くの企業経営者や経理担当者にとって、この新税制は喫緊の関心事です。
本コラムでは、防衛特別法人税の導入目的や仕組み、特に中小企業への影響、そして適用時期や申告・納付のポイントまで、企業が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
1. 防衛特別法人税の概要と導入の目的
防衛特別法人税は、日本の防衛力強化に必要な財源を安定的に確保するために、法人に対して一時的に(または継続的に)追加で課される国税です。
導入の目的と背景
防衛特別法人税の最大の目的は、日本の防衛力強化にかかる費用を賄うことです。
近年、国際情勢の緊張が高まる中、政府は防衛予算を増やし、防衛力を強化する方針を打ち出しました。この財源を賄うため、既存の税制に上乗せする形で新税が創設されることになりました。
過去には、東日本大震災の復興財源確保のために「復興特別法人税」が導入されましたが、防衛特別法人税は、現時点で終了時期が明確に定められていないため、恒久的な税制として長期的に適用される可能性があります。
防衛力強化のための「税制措置」全体像
防衛力強化の財源確保のための税制措置は、法人税だけでなく、以下の複数の税目(多角的アプローチ)にわたって実施される予定です。
- 法人税:防衛特別法人税を創設し、法人税額の一部に付加税として課税。
- 所得税:復興特別所得税の税率を引き下げ(2.1%から1.0%へ)、そのうち1%分を防衛財源に充てる措置(課税期間の延長も検討)。
- たばこ税:税率を段階的に引き上げ、増収分を財源に充当。
防衛特別法人税は、この中でも企業に直接的な負担を求める中核的な措置となります。
適用開始時期
防衛特別法人税は、2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定です。
- 3月決算の企業:2027年3月期(2026年4月1日~2027年3月31日)から適用。
- 12月決算の企業:2027年12月期(2027年1月1日~2027年12月31日)から適用。
企業は、この施行開始日までに納税資金の確保や税務戦略の見直しといった準備を進める必要があります。
2. 課税対象と計算方法
防衛特別法人税は、原則として法人税を納めるすべての法人が対象となりますが、既存の法人税に上乗せして課されます。その計算には「基礎控除額」が設けられており、すべての法人に一律に負担を求めるわけではありません。
課税対象となる税額(基準法人税額)
防衛特別法人税は、企業の「所得」に直接課されるのではなく、「基準法人税額」に税率を乗じて計算されます。
- 基準法人税額とは、所得税額控除や外国税額控除などを適用する前の、本来の法人税額を指します。
計算方法の基本(基礎控除500万円)
防衛特別法人税の計算式は以下の通りです。
防衛特別法人税額=(基準法人税額−500万円(基礎控除額))×4%(税率)
基礎控除による中小企業への実質免除
この計算式で重要なのが、一律500万円の基礎控除額です。
- 基準法人税額が500万円以下の法人:控除額を超えないため、防衛特別法人税額はゼロになります。
- 基準法人税額が500万円を超える法人:500万円を超えた部分にのみ4%の税率が適用されます。
これにより、法人税額が500万円以下の企業は、実質的に防衛特別法人税の課税対象外となります。所得(利益)が約2,400万円前後の企業は実質的に免除されることになります。
実質的な増税率
防衛特別法人税の税率は4%ですが、これは法人税額に対する付加税率です。通常の法人税率(原則23.2%)に乗じることで、実質的な税負担増加分を試算できます。
実質的な増税率≒法人税率×4%
例えば、法人税率が23.2%の企業の場合、実質的な増税は約0.93%(23.2% × 4%)となり、約1%程度の負担増と見込まれます。
3. 申告と納付:法人税と同じスケジュール
防衛特別法人税は、既存の法人税制度に組み込まれる形で運用されます。申告と納付のスケジュール、手続きは、原則として法人税と同じです。
申告・納付期限
- 確定申告:各課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、所轄の税務署長に申告書を提出し、納付します。
- 中間申告:法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税についても中間申告書を提出する必要があります、防衛特別法人税についても中間申告が必要です。
【重要!】 たとえ基準法人税額が500万円以下で、防衛特別法人税額が「0円」となる企業であっても、申告義務は免除されません。必ず専用の別表を作成し、0円申告を行う必要があるため、注意が必要です。
4. 企業への影響と事前対策
防衛特別法人税の導入は、企業のキャッシュフローや税務戦略に影響を与えます。特に、税効果会計を適用している企業は準備が欠かせません。
影響①:税効果会計の取り扱い
税効果会計を適用している企業(主に上場企業やその子会社など)は、税制改正が成立した事業年度の決算において、将来の課税所得を計算する際に防衛特別法人税の影響を反映させる必要があります。
実効税率(法定実効税率)の計算式に防衛特別法人税率が加わるため、税率の変更に伴う繰延税金資産・負債の計算見直しが必要です。経理・税務部門は、施行開始前の段階から対応準備を進める必要があります。
影響②:納税資金の確保と利益調整
基準法人税額が500万円を超える中堅・大企業では、純粋に税負担が増加するため、あらかじめ納税資金の確保を計画に組み込む必要があります。
また、決算時の利益調整の観点からも、法人税額を500万円以下に抑えるための投資や経費計上の戦略的な検討が重要になります。
影響③:地方税への影響は?
防衛特別法人税は「国税」であり、法人税の付加税として課されます。この税の創設自体が、法人事業税や法人住民税といった地方税の税率や計算に直接影響を与えるものではありません。
しかし、前述の通り、所得税額控除などの調整により基準法人税額自体が変わる場合があるため、法人税の確定申告書全体の整合性を確認することが不可欠です。
まとめ:施行前に準備すべきこと
防衛特別法人税は、2026年4月1日以降に開始する事業年度から適用が始まる新しい税制です。
| 項目 | 内容 | 企業がすべき対策 |
| 適用開始 | 2026年4月1日以後に開始する事業年度から | 施行日を把握し、納税資金計画を見直す。 |
| 課税対象 | 基準法人税額が500万円を超える部分 | 自社の法人税額を試算し、影響度を把握する。 |
| 中小企業 | 法人税額が500万円以下の企業は実質非課税 | 0円申告は必須なので、申告体制を整える。 |
| 申告義務 | 法人税と同じスケジュールで必ず申告が必要 | 申告漏れがないよう、別表一次葉一の作成手順を確認する。 |
法人税額が500万円以下の企業にとって直接的な金銭負担はないとしても、申告義務があること、そして税務の複雑さが増すことは間違いありません。施行開始に向けて、経理・税務担当者は最新の情報を確認し、準備を進めていくことが求められます。