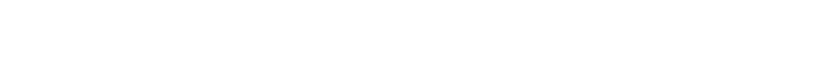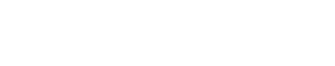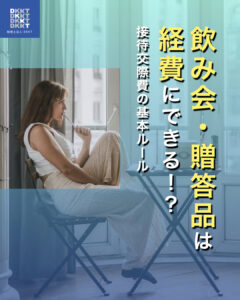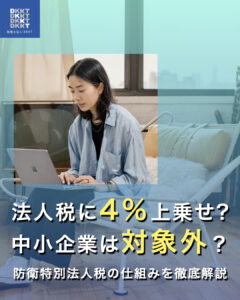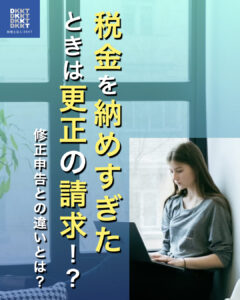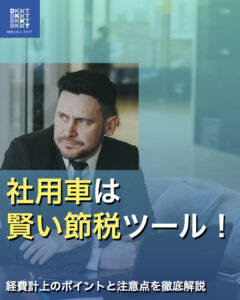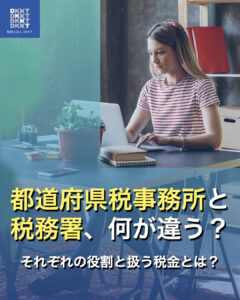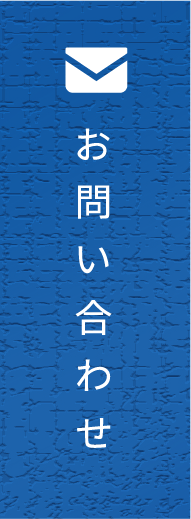予定納税は「いくらから」?突然の通知に慌てないための全知識
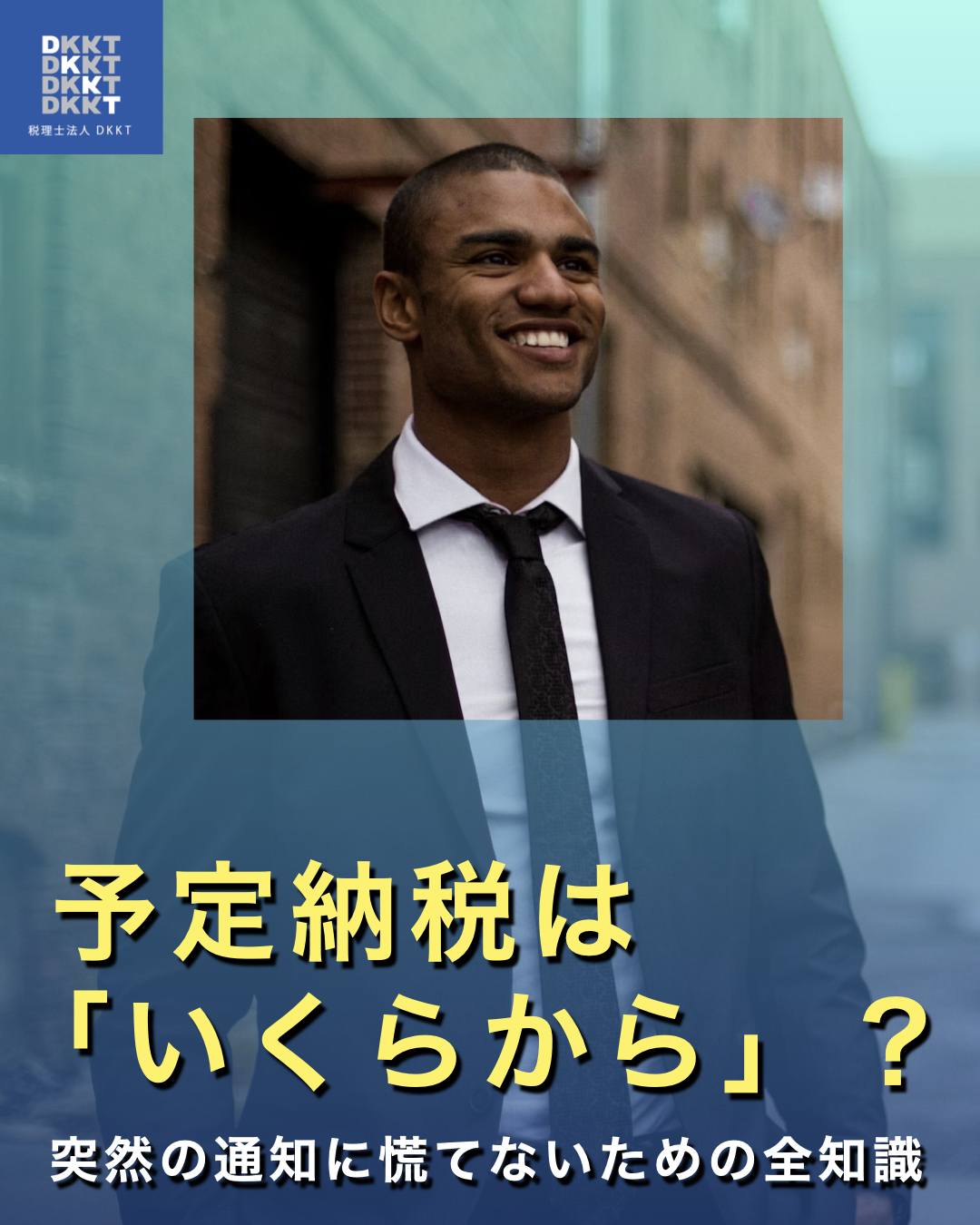
「決算を終えて税金を納めたばかりなのに、また税金の通知が来た…」
法人経営者や経理担当者にとって、**予定納税(中間納付)**は、年間の資金繰りを大きく左右する重要な課題です。これは、その年の税金の一部を事業年度の途中で前払いする制度ですが、その仕組みや計算方法を理解していないと、突発的な資金流出となり、キャッシュフローを圧迫する原因にもなりかねません。
本コラムでは、主に法人税に焦点を当て、予定納税(中間納付)の基本から、納付が義務付けられる基準、そして企業の経営状況に応じて選択できる二つの申告方法と、納付が難しい場合の対処法まで、必要な知識を徹底解説します。
1. 予定納税の基本|前払い制度の目的と対象税目
予定納税とは
予定納税とは、今期の確定申告で納める税金の一部を前払いする制度です。これは、国が年間の税収を安定させる目的と、納税者が確定申告時に税金を一括で納めることによる資金面の大きな負担を緩和するための措置として設けられています。
対象となる税目と基準
国税のうち、前事業年度の確定税額が一定額を超えた場合、予定納税(中間納付)が義務付けられます。
| 税目 | 前事業年度の確定税額・予定納税基準額 | 納付期間 |
| 法人税 | 20万円を超えている | 年1回(後述) |
| 消費税 | 48万円を超えている | 納税額に応じて年1~11回 |
| 所得税(個人事業主) | 15万円を超えている | 年2回(7月、11月) |
この予定納税で納めた税金は、確定申告の際に既に納めた税金として差し引かれます。払いすぎた場合は、確定申告後に還付されますので、最終的に1年間に納める税額に違いはありません。
予定納税の対象外となる法人
以下の法人は、前事業年度の確定税額が基準となるため、原則として予定納税の対象外となります。
- 設立初年度の法人:前事業年度の確定税額が存在しないため。ただし、吸収合併など特殊なケースで設立された法人は対象となる場合があります。
- NPO法人など公益法人:収益事業を行っていない場合など、法人税が非課税となる場合は対象外です(ただし、消費税については中間申告が必要になる場合があります)。
2. 法人税の予定納税(中間納付)のスケジュールと通知
法人税の中間納付は、法律によって納付期間が定められており、事業年度の途中で一度だけ納付します。
納付期間
法人税の中間納付期間は、事業年度開始以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内です。この期間に申告書を提出し、税金を納める必要があります。
- 例:12月末決算の会社の場合
- 事業年度開始:1月1日
- 6ヵ月経過日:7月1日
- 納付期間:7月1日〜9月30日
通知書の確認と資金繰り
予定納税額は、税務署が前事業年度の確定申告書に基づいて計算し、納付期間の前に紙の通知書で送付されます。
通知書が送付されなくなった場合でも対応できるよう、資金繰りに余裕を持つためにも、前事業年度の確定申告時に、今期の予定納税額を自社で試算しておくことを強くおすすめします。
3. 法人税の中間納付:2つの申告・納付方法
法人税の中間納付では、「予定申告」と「仮決算」という二つの方法から、会社にとって有利な方を選択できます。会社の経営状況によって使い分けるのが一般的です。
方式①:予定申告(前年実績方式)
予定申告は、前事業年度の確定税額をもとにして今期の予定納税額を算出する方法です。
- 算出方法:
今期の予定納税額=前事業年度の確定法人税額×6ヵ月÷前事業年度の月数
- メリット:前事業年度の確定税額だけで算出できるため、経理処理がかなり簡略化されます。書類作成の手間がほとんどありません。
- みなし申告の特例:予定申告書は、提出しなくても罰則がありません。納付期間内に納付さえすれば、申告書は提出したものと見なされます(みなし申告)。ただし、納税そのものは必須です。
方式②:仮決算
仮決算は、事業年度開始から6ヵ月間を1つの事業年度と見なして決算を行う方法です。
- 算出方法:事業年度前半6ヵ月の実績に基づき、通常の決算と同様に所得を計算し、納税額を算出します。
- メリット:前事業年度に比べて大きく利益が落ち込んでいる場合、予定申告よりも予定納税額を大幅に減額できる可能性があります。キャッシュフロー改善に直結します。
- デメリット:通常の決算とほぼ同じ内容の書類(法人税申告書、財務諸表、勘定科目内訳明細書、株主資本等変動計算書など)を作成・提出する必要があり、コストや経理処理の手間がかかります。
【選択の判断基準】
前期と業績があまり変わらない、または前期より利益が大幅に増えている場合は、事務負担の少ない予定申告を採用しましょう。前期より大幅に利益が落ち込んでいる場合は、仮決算を採用して納税額を減らすメリットがあります。
4. 納付期限厳守と納付が難しい場合の対処法
納付期限を過ぎると延滞税が発生
法人税の予定納税は、納付期限を過ぎると延滞税という罰則的な税金が発生します。延滞税は、延滞日数に比例して税額が増えるため、必ず期限内に納付しなければなりません。
予定納税の支払方法
予定納税の支払いには、現在、利便性の高い様々な方法が利用できます。
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- クレジットカード納付
- コンビニ納付(QRコード、バーコード)
- 金融機関や税務署での直接納付
納付が難しい場合の対策
予定納税額は前期の納税額をベースにしているため、今期の売上が急激に低迷した場合、資金繰りが厳しくなることがあります。
- 仮決算の採用:上半期の売上が前期を大幅に下回っている場合は、まず仮決算を行い、予定納税額を減額できないか検討しましょう。
- 換価の猶予申請:仮決算によっても納税額を賄えない場合、「換価の猶予申請」を行うことで、予定納税額を分割納付できる可能性があります。この申請には、納付期限から6ヵ月以内に所轄の税務署へ必要書類を提出する必要があります。
まとめ
予定納税は、法人にとって資金繰りの上で大きなウェイトを占めます。
| 項目 | 法人税予定納税の重要チェックポイント |
| 納付基準 | 前期法人税額が20万円を超えているか |
| 納付期限 | 事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内 |
| 未納対策 | 仮決算の検討、または換価の猶予申請 |
年に何度も税務に関する義務を抱える法人にとって、予定納税(中間納付)や確定申告の事務負担は小さくありません。仮決算の検討や、節税対策のアドバイスを受けるためにも、税務全般を税理士に委託することも検討してみてください。